2024年1月10日 (オンライン)
2024年1月10日に開催された、アジア太平洋地域における災害リスク軽減のための気候変動予測に関するウェビナーシリーズ第2回では、ネパールにおける予測研究の成果と気候変動関連データの活用について取り上げられました。このウェビナーでは、気候変動予測先端研究プログラム(SENTAN)プロジェクトによりネパールから2人の専門家が招かれ、情報と経験が共有されました。
ポカラ大学工学部のビナヤ・クマール・ミシュラ教授は、ネパールのバグマティ川における洪水頻度の変化予測について発表しました。カトマンズ渓谷一帯に広がるバグマティ川流域はコカナの上流に位置し、近年壊滅的な洪水が発生するようになりました。そのため、ポカラ大学では、気候変動シナリオ下での洪水流量の変化を評価するために、水文工学センター水文モデリングシステム(HEC-HMS)を設置しました。カトマンズ渓谷の将来の洪水リスクを評価するために、非常に高解像度の非静力学地域気候モデル(NHRCM)の降水出力が用いられました。この研究から、以下のような結果がもたらされました。
1)地域気候モデル(RCM)の降水量出力において、極端な降水量の増加が確認された。
2)将来の気候条件における降水量の極端な増加は、カトマンズ渓谷における洪水リスクの増大を示している。
ネパール政府水文気象局(DHM)の気候課長であるビブティ・ポカレル氏は、DHMが提供する気候サービス情報について説明を行いました。ポカレル氏からは、DHMがネパールの降水量と気温を監視し、干ばつや熱波、異常気象の切迫した情報を提供していることの発表がありました。DHMが作成する気候データは、気候予測に利用されるだけでなく、気候変動に関する国家基本計画や政策に反映されます。さらに、気候サービス情報は、航空、農業、水、エネルギー、保健、防災(DRR)の各部門に提供されています。しかし、気候情報サービスには限界やギャップがあり、ポカレル氏は、研究能力や設備に限界のため、気候情報の質は高くないと指摘しました。例えば、DHMは現在、統計的ダウンスケーリングを利用していますが、動的ダウンスケーリングを利用する能力はないため、SENTANのようなパートナーの支援は非常にありがたいとの発言がありました。
このウェビナーでは、下記の研究者による講演が行われ、ウェビナーで提起された重要なポイントを紹介し、SENTANプロジェクトとDHMネパールのさらなる協力を促しました。
1)京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 教授 森信人氏
2)気象庁気象研究所応用気象研究部第二研究室 室長 中江川敏行氏
3)気象庁気象研究所応用気象研究部第一研究室 室長 村田明彦氏
4)水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)グループ長、及び水のレジリエンスと災害に関するプラットフォーム代表 森範行氏
5)京都大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 水工学講座 水文・水資源学分野 教授 立川 康人
このウェビナーは、神戸大学都市安全研究センター リスク・コミュニケーション研究部門安全コミュニケーショングループ准教授の小林健一郎氏と、アジア防災センター(ADRC)主任研究員のジェリー・ポトゥタン氏が共同進行役を務めました。本ウェビナーのビデオ録画と資料は以下のウェブサイトに掲載されています。
(2024/01/17 15:00)















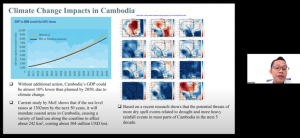




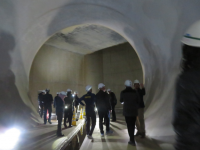

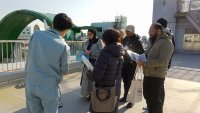








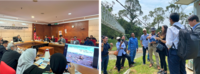










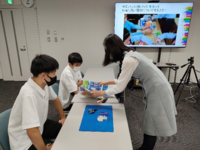





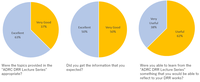




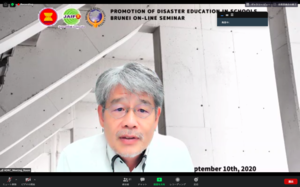


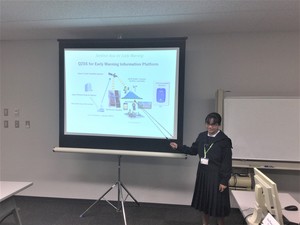
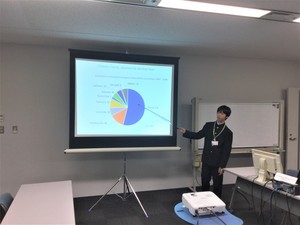







-thumb-300x166-1431.jpg)
-thumb-300x199-1428.jpg)






























