2024年11月12~13日(ベトナム、ハノイ)
2024年11月12―13日にベトナムのハノイにおいて、ベトナム堤防管理・防災局(VDDMA)、内閣府、アジア防災センター(ADRC)の共催でアジア防災会議(ACDR2024)が開催されました。前号でお伝えしました通り、会議の詳細についてお知らせします。なお、本会議の資料は、以下のウェブサイトからご覧いただけます。
ACDR2024ウェブサイト:https://www.adrc.asia/acdr/2024_index.php
<開会式>
ベトナム農業農村開発省のグエン・ホン・ヒップ副大臣、内閣府貫名功二大臣官房審議官(防災担当)、ADRCの濱田政則センター長がそれぞれ、災害リスク軽減(DRR)におけるADRCの役割の重要性、災害対策強化の必要性、最近の災害の影響と課題について述べました。
<ラウンド・テーブル>
VDDMAのドアン・ティ・トゥエ・ガー国際協力・科学技術部長による司会により、ラウンド・テーブルでは、ブルネイ、カンボジア、日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナムの15メンバー国が、「仙台防災枠組(SFDRR)における気候危機へのレジリエンスに関する行動実施における課題と進捗状況」について発表を行いました。全体として、声明は、気候危機に対するレジリエンス強化に関する共通の戦略を強調しました。
- 気候行動のための支援メカニズムの強化
- 気候危機軽減のための資金調達オプションの強化
- 気候レジリエンス強化のための科学技術の活用
<セッション1:洪水・鉄砲水リスク情報の高度化>
山口大学三浦房紀名誉教授の司会のもと、洪水および鉄砲水のリスク情報を強化するための最新技術が紹介されました。
- キプロス大学のデメトリオス・エリアデス研究助教授は、洪水モデリングや洪水リスク評価に役立つ、リスクの監視と予測のための人工知能対応システムの例や、特にセルラーネットワークやWiFiへのアクセスが制限されている地域で、LPWAN通信技術が洪水リスク情報を広めるのにどのように役立つかを紹介しました。
- 神奈川大学の朱牟田善治教授は、災害対応と復旧のためのセンシング技術を紹介しました。例えば、電力ライフラインのリスク評価管理システム(RAMP)では、時間的および空間的補間の性能を向上させるために、様々なセンサーが利用されています。
- 山口大学の三浦房紀名誉教授は、防災のための衛星データ利用の現状について、様々な協力形態があることを紹介しました。この地域にはセンチネルアジアが活動し、日本では衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)があります。しかし、サービス提供においては、公的衛星と民間衛星が独立して稼働しています。「防災訓練」の結果が示すように、個別に提供される衛星サービスは効果が低いことがわかりました。その有効性を高めるために、「衛星ワンストップシステム」を導入し、防災における衛星の役割を最適化することが紹介されました。
- インドネシア大学地理学部のマシタ・ディウィ・マンディニ・マネッサ講師は、インドネシアのマゲラン県における農業システムの地すべりや洪水を予測する空間機械学習の役割を強調し、空間機械学習を用いることで、生産性の高い農地の約38%が高い洪水リスクにさらされることが予測されると発表しました。
- ベトナムのイエンバイ省農業農村開発部のグエン・スアン・サン副部長は、台風11号(ヤギ) による同省の地すべりの影響を報告し、教訓として、地すべりの予測と早期警報システムの技術を向上させる必要性を挙げました。
- ベトナムのカオバン省農業農村開発部灌漑部門のホアン・ミン・トゥアン災害管理局長は、同省における台風ヤギへの対応の教訓を共有し、ドローンなどの活用を含め、捜索救助活動のためのより良い技術の必要性を挙げました。
<セッション2:将来リスク分析に基づく洪水対策の強化 - アジアにおける災害リスク軽減(DRR)と気候変動適応(CCA)の推進>
本セッションは、グエン・ニタ・フン南部水資源研究所副所長が司会を務め、DRR-CCAのための洪水対策について、改善のための原則とアプローチが共有されました。
- ベトナム農業農村開発省の鈴木高防災アドバイザー(およびJICA専門家)は、「カイゼン」の概念を適用することで、科学的な河川改修や統合的な流域管理などを通じて、洪水対策を改善できることを強調しました。
- 東北大学の小野高宏特任教授(および東京海上ホールディングス株式会社 ビジネスデザイン部部長)は、「事前投資」の利点を強調し、事業継続計画(BCP)や防災行動計画などの取り組みが、事後の経済的収縮を軽減し、災害後の回復を加速させる事前投資の例として挙げました。
- 韓国行政安全部のジュンハ・キムチーム長は、韓国における洪水対策の実施には、積極的な災害準備と協働的な災害管理が含まれていると報告しました。積極的な災害準備とは、死傷者を減らすための先制的な避難を実施する際の機関の準備性を確保すること、協働的な災害管理とは、災害ガバナンスにすべての関係者を関与させることを指します。
- タイの災害管理センターのアングスマリン・アングスシンハ防災専門家は、タイ北部における洪水状況と、防災局(DDPM)が洪水状況に対処するために適用した住民主体のアプローチである「ソリューション・フレームワーク」を紹介しました。
- ベトナムのハザン省農業農村開発部のレー・アン・ダン灌漑部門長は、同省における台風ヤギによる影響は深刻であったにもかかわらず、緊急対応のための外部支援は限られていたことが報告されました。この課題に対処するため、同省は地域社会の能力を最大限に活用するために、地域に根ざした「ファースト・レスポンダー」の訓練を継続していくとしています。
<ベトナムの災害と防災に関する特別セッション>
特別セッションでは、ベトナム農業農村開発省の鈴木防災アドバイザー(およびJICA専門家)が司会を務め、ベトナムの災害と災害管理の概要が紹介されました。台風ヤギによる洪水、鉄砲水、地すべりを中心に、ベトナムにおける災害管理の現状と課題が示されました。
- VDDMAのグエン・トゥアン・トゥン氏は、過去10年間のベトナム北部山岳地域における鉄砲水と地すべりの状況を報告しました。将来の影響を軽減するための提言として、通信システムの強化、住民意識の向上、対応のための地域能力の構築、詳細で正確な地域別予測、早期警報システム、世帯レベルの災害管理計画などが挙げられました。
- ラオカイ省のクアン・ヴァン・ヴェト氏は、台風ヤギが人、財産、インフラに深刻な被害を与え、社会活動を混乱させたことを報告しました。将来、同様の災害の影響に効果的に対処するために、インフラの強靭化、予測と早期警報システムの改善、データ収集とリスク分析の強化などが言及されました。
- ソンラ省のルオン・カック・キエン氏は、日本政府とベトナム政府の技術協力の下、同省で試験的に行われている鉄砲水防止のためのパイロットモデルを紹介しました。
- イエンバイ省のファム・クオック・フン氏は、日本政府とベトナム政府の技術協力の下、同省のトラムタウ地区で試験的に実施されている地すべり早期警報に関する能力構築事業を紹介しました。
- クアンニン省のドアン・マン・フオン氏は、台風ヤギが同省の農業生産に深刻な影響を与え、人々の生活に影響を与えたことを報告しました。課題に対処するための行動として、子供や学生の学費、農業部門のニーズ、損壊した家屋の修理、水没した漁船の解体、持続可能な水産養殖の開発に対する支援などが挙げられました。
- 南部水資源研究所のグエン・ギア・フン氏は、メコンデルタにおける河岸浸食と海岸浸食への対処における課題を発表しました。
- VDDMAのゴ・フー・フイ氏は、ベトナム災害監視システム(VNDMS)を紹介しました。これは、様々な省庁、ライン機関、組織、地方自治体とのデータ統合と接続を通じて、災害予防・管理(DPC)管理をサポートするシステムです。
- VDDMAのダム・チー・ホア氏は、「災害管理におけるASEANの予測的行動の強化に関するハロン閣僚声明」の概要を説明し、DRRのための国際協力におけるベトナムの役割を示しました。
<閉会式>
閉会の挨拶では、VDDMAのファム・ダック・ルアン長官、内閣府貫名大臣官房審議官(防災担当)、前日のステアリング・コミッティで新任されたADRCの三浦房紀センター長それぞれにより、ADRCが今後もメンバー国と協力し、気候変動による影響に配慮したDRR活動の推進、およびSFDRRの残り5年間の役割の重要性についての期待を述べられ、本会議は閉会しました。
(2024/11/20 15:00)













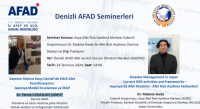

































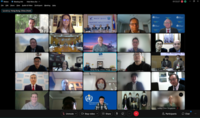
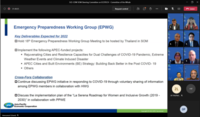





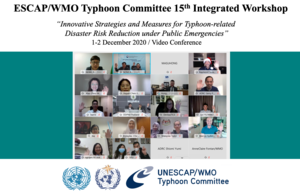














-thumb-300x225-1570.jpg)
















































