2025年2月28日
ADRCは、災害データの統計的・分析的視点を提供するため、毎年「自然災害データブック」(英語版のみ)を発行しています。最新の2023年度版をはじめ、これまでのデータブックは以下のサイトからご覧いただけます。
ADRC「自然災害データブック2023」:
https://www.adrc.asia/publications/databook/DB2023_e.php
(2025/2/28 15:00)

2025年2月28日
ADRCは、災害データの統計的・分析的視点を提供するため、毎年「自然災害データブック」(英語版のみ)を発行しています。最新の2023年度版をはじめ、これまでのデータブックは以下のサイトからご覧いただけます。
ADRC「自然災害データブック2023」:
https://www.adrc.asia/publications/databook/DB2023_e.php
(2025/2/28 15:00)
2025年2月28日
災害の記録や教訓を将来の世代や今後大災害が予想される他の地域のために残すことは重要です。ADRCは、衛星リモートセンシングを災害管理に適用するためのグッドプラクティスを収集する取り組みを支援してきました。その一つである2011年の東日本大震災の記録「2011年東日本大震災の緊急対応への国際協力による宇宙からの支援の記録」は、ADRC客員研究員の加来一哉博士が執筆し、2023年11月にケンブリッジ・スカラーズ・パブリッシングから出版されました。
この本は、日本に対する各国や国際社会からの寛大で友好的な支援の記録です。2011年の東日本大震災の際には、14の国と地域から27機の衛星が繰り返し宇宙から被災地を観測し、災害対応活動を支援しました。地震とそれに続く津波への対応を通じて、国際協力による宇宙からの対応が大規模災害時の救援活動を効果的に支援できることが実証されました。
本書は、2011年の東日本大震災や2006年から2014年までのセンチネル・アジア(SA)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の活動を検証し、災害対応支援に衛星リモートセンシングを適用するための要件を導き出しています。将来の災害に備えようとする人々にとって、この本はリマインダーとして役立つでしょう。また、本書は災害管理への衛星リモートセンシングの適用に関する教科書としても利用できます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
ハードカバーとペーパーバック:
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4636-3
電子書籍:
(2025/02/28 15:00)
2024年11月30日
センチネル・アジア(SA) は、宇宙コミュニティ(宇宙機関)、災害管理コミュニティ(ADRC とそのメンバー機関、災害管理機関)、国際機関、学術機関(大学、研究機関、技術機関)間の連携の枠組みです。ADRCとそのメンバーを通じた災害管理コミュニティとの連携は、当初からSAの主要ビジョンの一部でした。アジア・太平洋地域宇宙機関会議 (APRSAF)の枠組みの下で、2004年に提案され、2005年に実施が合意され、2006年に実施と運用が開始され、現在も運用されています。
2024年11月、ケンブリッジ・スカラーズ・パブリッシングから「センチネル・アジア10周年記念:アジア・太平洋における宇宙ベースの災害管理支援」というタイトルの本が出版されました。これは、ADRCの客員研究員である加来一哉博士、ADRCのプロジェクト・ディレクターである鈴木弘二氏らによって執筆されました。
この本は、2004年の構想発足から10年間のSAの活動をまとめたもので、10周年を記念しています。この本では、SAの歴史、枠組み、実施方法、運営方法、成果を紹介しており、地域のパートナーが建設的に協力して衛星リモートセンシングを適用し、地域の災害管理を支援してきた優れたケーススタディを提供し、SAのさらなる発展に貢献するとともに、他の地域での災害対応に関する同様の国際協力の参考になるでしょう。
この本の印税は、災害管理活動に寄付されます。詳細については、以下をご覧ください。
ハードカバー:https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-0364-1715-4
(2024/12/07 15:00)
2024年11月17日~12月14日
インドネシアは日本と同様に地震が頻発しており、過去の地震発生においては多くの貴重な人命や財産が失われてきました。日本では全国的に地震早期警報システムが整備されていますが、インドネシアにおいては今後の課題となっています。
そこで、アジア防災センター(ADRC)はインドネシアにおいて災害情報を扱う主要機関の一つであるインドネシア気象庁(BMKG)からの依頼を受け、BMKG職員の能力向上を目的とした研修業務を実施しました。期間は2024年11月17日から12月14日に実施されました。BMKGの職員30名が参加し、日本の防災関係機関に訪問し講義や実習などが行われました。
研修では、東京大学、東北大学、京都大学などからは地震学や日本の早期警報システム、近年の研究事例などの講義を受講しました。内閣府や藤沢市においては、行政の防災の取り組みについて学びました。また、東日本大震災の被災地を視察し、同災害に関する震災遺構や博物館などを訪問しました。さらに、鉄道や地図、警報装置や通信を取り扱う民間企業からも、現在の最新の地震防災対策などについて講義を受けました。
研修員は日本における防災の取り組み、また主要テーマである地震早期警報システムの整備における最新の取り組みなどについて、学ぶことができました。この経験や知識が、今後のインドネシアにおける同システムの整備に寄与されることを期待しています。
(2024/12/21 15:00)
2024年11月12~13日(ベトナム、ハノイ)
2024年11月12―13日にベトナムのハノイにおいて、ベトナム堤防管理・防災局(VDDMA)、内閣府、アジア防災センター(ADRC)の共催でアジア防災会議(ACDR2024)が開催されました。前号でお伝えしました通り、会議の詳細についてお知らせします。なお、本会議の資料は、以下のウェブサイトからご覧いただけます。
ACDR2024ウェブサイト:https://www.adrc.asia/acdr/2024_index.php
<開会式>
ベトナム農業農村開発省のグエン・ホン・ヒップ副大臣、内閣府貫名功二大臣官房審議官(防災担当)、ADRCの濱田政則センター長がそれぞれ、災害リスク軽減(DRR)におけるADRCの役割の重要性、災害対策強化の必要性、最近の災害の影響と課題について述べました。
<ラウンド・テーブル>
VDDMAのドアン・ティ・トゥエ・ガー国際協力・科学技術部長による司会により、ラウンド・テーブルでは、ブルネイ、カンボジア、日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナムの15メンバー国が、「仙台防災枠組(SFDRR)における気候危機へのレジリエンスに関する行動実施における課題と進捗状況」について発表を行いました。全体として、声明は、気候危機に対するレジリエンス強化に関する共通の戦略を強調しました。
- 気候行動のための支援メカニズムの強化
- 気候危機軽減のための資金調達オプションの強化
- 気候レジリエンス強化のための科学技術の活用
<セッション1:洪水・鉄砲水リスク情報の高度化>
山口大学三浦房紀名誉教授の司会のもと、洪水および鉄砲水のリスク情報を強化するための最新技術が紹介されました。
- キプロス大学のデメトリオス・エリアデス研究助教授は、洪水モデリングや洪水リスク評価に役立つ、リスクの監視と予測のための人工知能対応システムの例や、特にセルラーネットワークやWiFiへのアクセスが制限されている地域で、LPWAN通信技術が洪水リスク情報を広めるのにどのように役立つかを紹介しました。
- 神奈川大学の朱牟田善治教授は、災害対応と復旧のためのセンシング技術を紹介しました。例えば、電力ライフラインのリスク評価管理システム(RAMP)では、時間的および空間的補間の性能を向上させるために、様々なセンサーが利用されています。
- 山口大学の三浦房紀名誉教授は、防災のための衛星データ利用の現状について、様々な協力形態があることを紹介しました。この地域にはセンチネルアジアが活動し、日本では衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)があります。しかし、サービス提供においては、公的衛星と民間衛星が独立して稼働しています。「防災訓練」の結果が示すように、個別に提供される衛星サービスは効果が低いことがわかりました。その有効性を高めるために、「衛星ワンストップシステム」を導入し、防災における衛星の役割を最適化することが紹介されました。
- インドネシア大学地理学部のマシタ・ディウィ・マンディニ・マネッサ講師は、インドネシアのマゲラン県における農業システムの地すべりや洪水を予測する空間機械学習の役割を強調し、空間機械学習を用いることで、生産性の高い農地の約38%が高い洪水リスクにさらされることが予測されると発表しました。
- ベトナムのイエンバイ省農業農村開発部のグエン・スアン・サン副部長は、台風11号(ヤギ) による同省の地すべりの影響を報告し、教訓として、地すべりの予測と早期警報システムの技術を向上させる必要性を挙げました。
- ベトナムのカオバン省農業農村開発部灌漑部門のホアン・ミン・トゥアン災害管理局長は、同省における台風ヤギへの対応の教訓を共有し、ドローンなどの活用を含め、捜索救助活動のためのより良い技術の必要性を挙げました。
<セッション2:将来リスク分析に基づく洪水対策の強化 - アジアにおける災害リスク軽減(DRR)と気候変動適応(CCA)の推進>
本セッションは、グエン・ニタ・フン南部水資源研究所副所長が司会を務め、DRR-CCAのための洪水対策について、改善のための原則とアプローチが共有されました。
- ベトナム農業農村開発省の鈴木高防災アドバイザー(およびJICA専門家)は、「カイゼン」の概念を適用することで、科学的な河川改修や統合的な流域管理などを通じて、洪水対策を改善できることを強調しました。
- 東北大学の小野高宏特任教授(および東京海上ホールディングス株式会社 ビジネスデザイン部部長)は、「事前投資」の利点を強調し、事業継続計画(BCP)や防災行動計画などの取り組みが、事後の経済的収縮を軽減し、災害後の回復を加速させる事前投資の例として挙げました。
- 韓国行政安全部のジュンハ・キムチーム長は、韓国における洪水対策の実施には、積極的な災害準備と協働的な災害管理が含まれていると報告しました。積極的な災害準備とは、死傷者を減らすための先制的な避難を実施する際の機関の準備性を確保すること、協働的な災害管理とは、災害ガバナンスにすべての関係者を関与させることを指します。
- タイの災害管理センターのアングスマリン・アングスシンハ防災専門家は、タイ北部における洪水状況と、防災局(DDPM)が洪水状況に対処するために適用した住民主体のアプローチである「ソリューション・フレームワーク」を紹介しました。
- ベトナムのハザン省農業農村開発部のレー・アン・ダン灌漑部門長は、同省における台風ヤギによる影響は深刻であったにもかかわらず、緊急対応のための外部支援は限られていたことが報告されました。この課題に対処するため、同省は地域社会の能力を最大限に活用するために、地域に根ざした「ファースト・レスポンダー」の訓練を継続していくとしています。
<ベトナムの災害と防災に関する特別セッション>
特別セッションでは、ベトナム農業農村開発省の鈴木防災アドバイザー(およびJICA専門家)が司会を務め、ベトナムの災害と災害管理の概要が紹介されました。台風ヤギによる洪水、鉄砲水、地すべりを中心に、ベトナムにおける災害管理の現状と課題が示されました。
- VDDMAのグエン・トゥアン・トゥン氏は、過去10年間のベトナム北部山岳地域における鉄砲水と地すべりの状況を報告しました。将来の影響を軽減するための提言として、通信システムの強化、住民意識の向上、対応のための地域能力の構築、詳細で正確な地域別予測、早期警報システム、世帯レベルの災害管理計画などが挙げられました。
- ラオカイ省のクアン・ヴァン・ヴェト氏は、台風ヤギが人、財産、インフラに深刻な被害を与え、社会活動を混乱させたことを報告しました。将来、同様の災害の影響に効果的に対処するために、インフラの強靭化、予測と早期警報システムの改善、データ収集とリスク分析の強化などが言及されました。
- ソンラ省のルオン・カック・キエン氏は、日本政府とベトナム政府の技術協力の下、同省で試験的に行われている鉄砲水防止のためのパイロットモデルを紹介しました。
- イエンバイ省のファム・クオック・フン氏は、日本政府とベトナム政府の技術協力の下、同省のトラムタウ地区で試験的に実施されている地すべり早期警報に関する能力構築事業を紹介しました。
- クアンニン省のドアン・マン・フオン氏は、台風ヤギが同省の農業生産に深刻な影響を与え、人々の生活に影響を与えたことを報告しました。課題に対処するための行動として、子供や学生の学費、農業部門のニーズ、損壊した家屋の修理、水没した漁船の解体、持続可能な水産養殖の開発に対する支援などが挙げられました。
- 南部水資源研究所のグエン・ギア・フン氏は、メコンデルタにおける河岸浸食と海岸浸食への対処における課題を発表しました。
- VDDMAのゴ・フー・フイ氏は、ベトナム災害監視システム(VNDMS)を紹介しました。これは、様々な省庁、ライン機関、組織、地方自治体とのデータ統合と接続を通じて、災害予防・管理(DPC)管理をサポートするシステムです。
- VDDMAのダム・チー・ホア氏は、「災害管理におけるASEANの予測的行動の強化に関するハロン閣僚声明」の概要を説明し、DRRのための国際協力におけるベトナムの役割を示しました。
<閉会式>
閉会の挨拶では、VDDMAのファム・ダック・ルアン長官、内閣府貫名大臣官房審議官(防災担当)、前日のステアリング・コミッティで新任されたADRCの三浦房紀センター長それぞれにより、ADRCが今後もメンバー国と協力し、気候変動による影響に配慮したDRR活動の推進、およびSFDRRの残り5年間の役割の重要性についての期待を述べられ、本会議は閉会しました。
(2024/11/20 15:00)
2024年9月7日(インドネシア、ジョグジャカルタ)
関西国際大学(KUIS: Kansai University of International Studies)がトヨタ財団の助成を受けて実施している「アジアにおける市民防災エンパワメントプログラムの共同開発」事業の一環として、2024年9月7日(土)にインドネシアのジョグジャカルタで、地元コミュニティと協力したICTを活用したコミュニティ防災訓練が実施され、ADRCはその事業実施のサポート機関として活動に参加しました。
洪水や火山灰の土石流などの災害が危惧されるジョグジャカルタ市内のCode川沿いのJogoyudanというコミュニティを対象とし、KUISと現地のUniversity of Atma Jaya Yogyakarta(UAJY)が自治体の防災機関(BPBD)およびコミュニティと調整して、双方の大学の学生が活動に参画する形で実施されました。準備期間が短かったことで十分な調整はできませんでしたが、避難訓練ではそれぞれが協力し、けが人、妊婦、身体障がい者をサポートして避難するなどの工夫した活動ができました。
訓練は、昨年度ADRCがマレーシアでのASEAN事業で導入したコミュニティとの災害時の情報共有システム(geoBingAn + WhatsAppのシステム)を活用し実施されました(ADRCハイライト368号、370号を参照)。このアプリは、普段使っているWhatsAppから登録することにより、登録者のWhatsAppへの一斉配信(Broadcast)と、WhatsAPPからのテキスト、写真、動画による情報収集が可能となるものです。WhatsAPP上で双方向の情報のやりとりを可能とする使い勝手のよいシステムです。
訓練中には、BPBDが従来から利用している無線での情報共有に加え、参加者からWhatsAppで情報を随時アップロードすることもできました。BPBDやコミュニティからも使い慣れているWhatsAppを利用して情報を共有するのはとても便利で使いやすいとの声がありました。訓練終了後にも、BPBDから今後の協力に関する質問もあり、また引き続きこのシステムを利用していきたいとの要望もありました。
前述のとおり、今回は事前の準備時間があまり取れず、自治体職員が十分にシステムを活用した活動まではできませんでしたが、ICTを活用した訓練の結果は、引き続き実施された国際ワークショップ「アジア市民防災推進会議(ACDRI)」において報告されました。次回のマレーシアの大学との活動で引き続きICTを活用した防災イベントを実施する予定です。
(2024/09/14 15:00)
2024年8月19日
カンボジアのハック・マオ氏(気候変動局局長)とセム・サブス氏(気候変動局気候変動情報管理副主任)によると、カンボジアの全コミューンの44%は、気候変動により引き起こされ、頻発や強度を増した洪水、干ばつ、暴風雨に対して脆弱となっています。海面上昇が1,302mmに達すると予測される2050年までに、カンボジアの沿岸地域の約242平方キロメートルが浸水し、3億400万米ドルの経済損失が生じると推定されています。もし政府が気候変動の影響に対抗するための追加的な行動を提示しなければ、2050年のGDP計画は10%減少することになります。
2024年8月19日に開催された第3回アジア太平洋地域における災害リスク軽減のための気候変動予測に関するウェビナー・シリーズでこのような発表があり、パネリストや参加者はカンボジアにおける気候変動対策と課題について関心を示しました。これに対し、マオ氏とサブス氏は、カンボジアは他の地域諸国と同様、気候変動に適応し、その影響を緩和するための政策や規制を制定していると述べました。例えば、1)2030年までに再生可能エネルギーの使用率を現在の62%から70%に引き上げる、2)2050年までにオートバイの70%、自動車の40%をEVにする、3)2050年まで毎年100万本の木を植え、森林被覆率60%を達成する、といった目標があります。しかし、主な課題は、これらが異常な洪水や暴風雨などの気候関連災害による具体的な影響を予測していないことであると説明しました。そのためには、ダウンスケールされた気候データが不可欠となっています。現在のところ、カンボジアの過去の気候データはあまりありません。この問題は、気候変動の影響を測定したり、正確な予測を行ったりするためのツールや技術が政府内に限られているために、さらに深刻になっています。
このような懸念を踏まえ、他のパネリストからは、カンボジアで進行中の気候変動対策を補完する可能性のある気候変動予測に関する取り組みやツールが紹介されました。森信人教授(京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門)は、SENTANプログラムについて紹介し、極端な水関連事象の影響評価や、アジア太平洋地域の国々にダウンスケールした地球表面温度の上昇に伴うハザードの変化の分析といった、カンボジアとの協力の可能性について発表しました。中江川敏行氏(気象庁気象研究所応用気象研究部第二研究室長)からは、高解像度モデルとスーパーコンピュータを用いた地域レベルでの将来の気候を予測するツールについて紹介がありました。村田明彦氏(気象庁気象研究所応用気象研究部第一研究室長)からは、局地的な気候変動をシミュレートするための動的ダウンスケーリングのツールや手法について発表がありました。森範行氏(水災害・リスクマネジメント国際センターグループ長)は、ハザード、被害、社会経済的要因のデータ統合を含む、水災害とレジリエンスに関する包括的なプラットフォームについて紹介しました。このプラットフォームでは、様々な機関がそれぞれの気候データを提供し、統合することで、効果的に影響を予測し、危険にさらされているコミュニティに早期警報を提供することができます。
最後に、立川康人教授(京都大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 水工学講座 水文・水資源学分野)は、アジア太平洋地域の国々が取り組んでいる気候変動対策に、SENTANプログラム(ツール、技術、データセットなど)が貢献できる可能性を強調しました。また、このウェビナーを通じて、SENTANプログラムとカンボジアの協力関係がさらに深まることを期待しました。
(2024/08/26 15:00)
2024年7月24-25日 (オンライン)
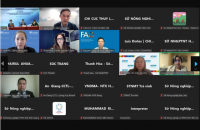 2024年7月24-25日、APECベトナムは「気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力の向上」をテーマとしたオンライン・ワークショップを開催しました。このワークショップは4つのテーマ別セッションで構成され、ADRCは「アジア太平洋における気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力:展望と課題」というテーマで、セッション1のモデレーターを務めました。
2024年7月24-25日、APECベトナムは「気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力の向上」をテーマとしたオンライン・ワークショップを開催しました。このワークショップは4つのテーマ別セッションで構成され、ADRCは「アジア太平洋における気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力:展望と課題」というテーマで、セッション1のモデレーターを務めました。
このセッションでは5人の専門家が発表を行いました。ベトナムからの2人の講演者は、猛烈な台風や頻発する洪水を引き起こす海面上昇など、国や地方レベルでの気候関連の課題についてそれぞれ報告を行いました。その他の専門家からは以下の報告が行われました。
1) 国連防災機関(UNDRR)は、仙台防災枠組が気候変動適応策と災害リスク軽減策を統合するためのガイダンスを提供していることを報告した。
2) 韓国は、高潮を監視・予測するための新しいツールが利用可能になったことを報告した。
3) オーストラリアは、アジア太平洋地域における沿岸レジリエンスのための戦略的パートナーシップの推進における取り組みについて報告した。
セッション2(テーマ:気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力強化に向けた取り組みの拡大)では、ADRCが「沿岸地域社会の回復力強化のための気候変動影響予測データの活用」について発表を行いました。ADRCは、多くの研究機関とともに、アジア太平洋地域の暴風雨・洪水災害と水資源に関する統合ハザードモデルの開発における気候変動予測先端研究プログラム(SENTAN4)への取り組みを紹介しました。特に、ADRCは、適応策や緩和策のための、地域ごとの気候変動影響予測データを作成するためのダウンスケーリングツールの活用について強調しました。
ADRCの本ワークショップへの参加は、地域レベルで気候関連の課題に取り組む他のエコノミーの経験や行動から学ぶ機会となりました。
(2024/08/01 15:00)
2024年7月24日 (トルコ、デニズリ)
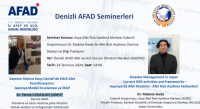 近年、ADRCとトルコの首相府災害緊急事態管理庁(AFAD)においては、国際会議の開催や現地調査など、多くの防災活動が実施されています。ADRCの池田主任研究員は、トルコ・デニズリのAFADで開催されたセミナーに参加し、日本における行政の防災の仕組みや、コミュニティレベルや国家レベルでの防災活動の事例について発表を行いました。また、AFADのFatma Canaslan Comut博士は、情報共有システムなど最近のAFADの防災活動について報告を行いました。参加者とともに、トルコにおけるより良いDRRを考えるための、有益な議論を行うことができました。
近年、ADRCとトルコの首相府災害緊急事態管理庁(AFAD)においては、国際会議の開催や現地調査など、多くの防災活動が実施されています。ADRCの池田主任研究員は、トルコ・デニズリのAFADで開催されたセミナーに参加し、日本における行政の防災の仕組みや、コミュニティレベルや国家レベルでの防災活動の事例について発表を行いました。また、AFADのFatma Canaslan Comut博士は、情報共有システムなど最近のAFADの防災活動について報告を行いました。参加者とともに、トルコにおけるより良いDRRを考えるための、有益な議論を行うことができました。
(2024/07/31 15:00)
2024年6月25日~28日 (韓国、ソウル)
 今年の台風委員会・防災作業部会(WGDRR)年次会合は、「『すべての人に早期警報システムを』イニシアチブ(EW4All):効果的な災害リスク軽減のためのギャップの解消」をテーマに、2024年6月25日から28日にかけて韓国のソウルで開催されました。ADRCは内閣府に代わり本会合に参加し、以下のような貢献と活動をしました。
今年の台風委員会・防災作業部会(WGDRR)年次会合は、「『すべての人に早期警報システムを』イニシアチブ(EW4All):効果的な災害リスク軽減のためのギャップの解消」をテーマに、2024年6月25日から28日にかけて韓国のソウルで開催されました。ADRCは内閣府に代わり本会合に参加し、以下のような貢献と活動をしました。
1)2023年にADRCが実施した防災活動、すなわちGLIDE、センチネル・アジア、準天頂衛星システム(QZSS)、トレーニング、ウェビナー、アジア防災会議(ACDR)、ウェブサイト、その他の情報共有活動などについて、それらの達成状況に焦点を当てて日本のメンバーレポートを発表した。
2)次回のACDR2024の主催者、テーマ、日程、開催地をWGDRRメンバーへ共有した。
3)ACDR2024のテーマに関連する技術発表として、韓国国家防災研究所(NDMI)から「ディープラーニングとセンサーデータを利用した都市浸水対応技術」及び国連アジア太平洋経済社会委員会(UN-ESCAP)から「『すべての人に早期警報システムを』イニシアチブにおける社会的インパクト予測の役割」が報告された。
4)GLIDE、ウェブサイト、オンライン・データベースを通じた情報共有におけるWGDRRとの継続的な協力関係を確認し、作業部会の年次活動計画(AOPs)に反映させることとした。
5)2024年7月24-25日に開催される「気候変動に対する脆弱な沿岸地域社会の回復力の向上」に関するAPECベトナムが主催するオンライン・ワークショップへのADRCの参加について、ベトナム側と協議した。
WGDRRは、UNESCAP/世界気象機関(WMO)台風委員会の下にある作業部会の一つで、アジア太平洋地域の14のメンバー(すなわち12カ国と2地域)で構成されています。
(2024/07/05 15:00)
2024年6月24日 ~ 25日 (ベトナム、ダナン)
2024年6月24日~25日、ベトナムのダナンでEPWGワークショップ「APECにおける災害脆弱コミュニティのための早期警報早期行動の強化」が開催されました。これは、APECの防災作業部会(EPWG)でベトナムのフォーカルポイントでもあるベトナム農業農村開発省堤防管理・防災局が主催したもので、APECのメンバーエコノミー間で自然災害リスク管理に関する専門的・技術的情報を共有することを目的としており、APEC域内の約30名の専門家が参加しました。
ADRCからは児玉美樹研究部長と塩見有美主任研究員が参加し、塩見主任研究員はセッション3「ベストプラクティスと教訓」の中で、「CBDRMと緊急事態管理のための最新技術の活用」と題したプレゼンテーションを行いました。本ワークショップを通じて、参加者は、脆弱なコミュニティに対する早期警報と早期行動に関するさまざまな教訓や意見を積極的に共有しました。
(2024/07/02 15:00)
2024年6月17日~8月8日
 アジア防災センター(ADRC)は、2024年6月17日から8月8日にかけて、JICA課題別研修「中央アジア・コーカサス総合防災」コースをJICA関西との協力により実施しました。カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの4か国から6名の防災担当行政官が参加し、災害対策の推進に向けた地方防災計画策定・実践の手法について学びました。
アジア防災センター(ADRC)は、2024年6月17日から8月8日にかけて、JICA課題別研修「中央アジア・コーカサス総合防災」コースをJICA関西との協力により実施しました。カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの4か国から6名の防災担当行政官が参加し、災害対策の推進に向けた地方防災計画策定・実践の手法について学びました。
前半の4週間はオンラインによる講義や演習を行い、後半の3週間は日本での対面研修を行いました。来日中は兵庫県、大阪府、奈良県の防災関連機関を訪問したほか、新潟県中越地震後の崩壊・地すべり対策や、富山県常願寺川流域の砂防・治水対策などの現場を視察しました。また、演習やディスカッションを通じて各国の地方防災計画案を作成しました。研修員の皆さんは熱心にプログラムに参加し、研修の成果をどのように自身の業務や自国の災害対策に活かしていくのか検討しました。
本研修実施にあたり、ご協力いただいた各関係機関のご担当者、講師の皆様に厚く御礼申し上げます。
(2024/08/15 15:00)
2024年6月10日 (オンライン)
2024年6月10日 国連防災緊急対応衛星情報プラットフォーム (UN-SPIDER)の地域支援事務所(RSO)会議がオンラインで開催されました。UN-SPIDERは、宇宙空間ベースの技術の防災や緊急対応の場面での利活用を促進するための多国間のプラットフォームであり、国連宇宙部(UNOOSA, United Nations Office for Outer Space Affairs)が支援しているプログラムです。UNOOSAは、国際連合において宇宙に関する政策を担当する機関です。本部はオーストリアのウィーンにあります。
また、RSOは、UN-SPIDERのプログラムを支援する地域単位のサポートオフィスのことです。2009年6月4日に国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)の第52回会議において、ADRCは、RSOの設立に関する協力合意文書にUNOOSAと共に署名し、以来RSOとして活動をしています。
6月10日のUN-SPIDERのRSOの会議では、内閣府宇宙戦略事務局がアジア大洋州地域の9カ国と連携して展開を検討している準天頂衛星の防災利用に関する事業の進捗状況について、ADRCのプロジェクト・ディレクターである鈴木弘二氏がプレゼンテーションを行いました。
この技術は、日本国が開発・運用しているGNSS(全球測位衛星システム)である準天頂衛星システム(日本名、みちびき)を利用して、防災関連情報を「みちびき」を介して伝達するものです。これは、通常の通信インフラが整備されていない地域や災害などの影響で通信インフラが途絶している状況下でも防災関連情報を提供することができる優れた技術であり、日本国内では2018年から一部運用が開始されています。この技術をアジア大洋州地域での社会実装を念頭にして、利用可能性についての調査やプロトタイプの受信機を現地に持ち込んでデモンストレーションを実施しているものです。
会議冒頭で、UN-SPIDERのプラットフォームで取り組まれてきた宇宙空間ベースの技術の防災利用の取り組みは、これまで光学衛星、SAR衛星関連のものであり、GNSS(QZSS、準天頂衛星)の技術の防災への活用の取り組みは極めてユニークであるという紹介がUN-SPIDERからありました。
(2024/06/17 15:00)
2024年5月20日 ~ 7月12日
アジア防災センター(ADRC)は、JICA関西と協力し、2024年5月20日から7月12日までJICA課題別研修「2024年度中南米総合防災コース」をオンラインと対面によるハイブリッド形式で実施しました。
本研修には、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、ペルーの中南米12ヶ国から14名の中央・地方政府防災担当者が参加しました。
参加者は、4週間のオンライン及び4週間の対面による講義、演習、視察に参加し、防災に関する日本の技術や経験を学びました。視察では、兵庫県や東京、岩手県の関連機関を訪問し、仁川地すべり資料館見学、兵庫県広域防災センター体験学習、北上川の洪水対策事業等の様々な対策を学びました。そして、地方防災計画策定のための8ステップ演習を通じ、自国・地域で実施するための地方防災計画案を策定しました。帰国後は、自国の防災対策を改善し、人命や経済の損失を削減していくために活躍することが期待されています。
当研修実施にあたり、御講義いただきました各関係機関・大学の皆様に厚く御礼申し上げます。今後とも引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(2024/07/19 15:00)
2024年5月9日(ブルネイ、バンダルスリブガワン)
2024年5月9日、ブルネイのバンダルスリブガワンにおいて第7回ASEAN 防災委員会(ACDM)+Japan会合が開催されました。ADRC笹原所長はプログラムの一環として、「日ASEAN防災行動計画2021-2025」を推進するために実施した「GLIDEを活用したデータベースのリンクと能力向上」および「ICTツールを活用したコミュニティ防災と災害対応」事業の最終報告を行いました。コミュニティ防災の活動に関しては、事業の対象国であったマレーシアの代表から、事業が成功裏に終了したことに対する感謝の言葉が述べられました。また、今後予定される活動として、これらのプロジェクトの次期フェーズの提案について説明を行いました。その他、「日ASEAN防災行動計画」の各活動の進捗状況の報告などがありました。さらに、ADRCは最終日に開催された現場視察に参加し、会議参加者同士の交流を深めました。
<メンバー国、関係機関等とのサイドミーティング>
今回ACDM + Japanのホスト国であるブルネイが5月1日にADRCに正式加盟したことから、ブルネイ国家災害管理センター(NDMC)の局長と今後の活動などに関する協議を行いました。また、マレーシア、ASEAN事務局、AHAセンターの代表とも会談を行いました。
(2024/05/16 15:00)
2024年3月14 ~ 15日(日本、能登半島)
2024年1月1日に発生した能登半島地震を受け、アジア防災センター(ADRC)は地震概要と被害や対応の概要について国や自治体による公式発表情報を英語でまとめた報告書を2月末まで更新していました(https://www.adrc.asia/publications/disaster_report/index.php)。そして地震発生から2か月半後の3月14-15日にADRC研究員と外国人客員研究員が能登半島を訪問し、地震と津波による被害を視察し、現在進行中の復興活動とその課題について検討を行いました。
避難、救援救助、復旧支援などの要となる道路については、動脈となる「のと里山海道」で重点的に復旧作業が進められていました。山間部を中心に土砂崩れで道路が被災している箇所が多々あり、1車線だけ仮復旧して通行していました。路面の損傷箇所は無数にあり、斜面も土のう積みの仮復旧状態であり、本格復旧には相当な時間がかかると思われました。また、関西、関東、東北、北海道など他都道府県警察が交通整理等の支援活動をしていました。
輪島市や珠洲市など被災中心域では多くの伝統的木造住宅が倒壊していました。瓦屋根の木造住宅は外国人客員研究員にとって身近な建築様式ではないのですが、重い瓦屋根が被害を大きくした原因であり、このような伝統的家屋の耐震性の強化促進策について意見が交わされました。
輪島市では延焼火災が発生した朝市通りや7階建てのビルの倒壊現場を視察しました。木造家屋密集地の災害対策や地震・津波発生時の消火対策など、多くの課題が突き付けられています。外国人客員研究員からは、2001年インドグジャラート地震との比較など、各国の建物やまちづくりとの比較もなされました。
地盤液状化が発生した各地ではマンホールが浮上がり電柱が傾斜していました。更に、震源域から100km以上離れた内灘町では多くの住宅が傾斜するなどの被害も見られました。
この他、地盤隆起により使用不能となった輪島市の漁港や、珠洲市の津波被災状況を視察するとともに、家屋の応急危険度判定の紙(緑、黄、赤)、給水車や炊き出し、応急診察所、仮設住宅建設状況など、復旧支援活動も視察し、今後の各国の地震防災対策について知見を得ました。
(2024/03/22 15:00)
2022年3月31日
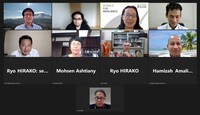
2020年12月1~2日(オンライン)
2006年以降、台風委員会(ESCAPとWMOの支援の下、アジア太平洋地域の14の加盟国で構成される政府間組織)は、気象、水文、防災の3分野にかかる「統合ワークショップ」(IWS)を毎年開催しています。IWSの主な目的は、現在および新たに発生している台風関連の問題/テーマについて話し合うことです。 本年の台風委員会第15回IWSは、「緊急事態における台風関連の災害リスク軽減のための革新的な戦略と対策」をテーマに掲げ、2020年12月1日から2日にかけオンラインで実施されました。
ADRCは、「コロナ禍の災害対応:最近の台風からの教訓」というタイトルの基調講演を行いました。発表では新型コロナウイルス感染症の大流行に加え、最近の台風災害への対応におけるフィリピン、インド、韓国の防災機関の活動に焦点が当てられました。
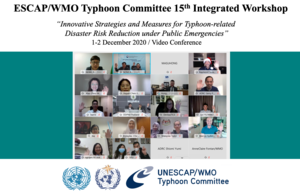
人々の移動の制限、社会的距離、マスク、フェイスシールドなどの顔面保護等の感染防止対策の必要性を鑑み、防災機関は新しい対応策を導入しました。例えば (i)より多くの避難所の指定(ii)新型コロナ感染症に感染した避難者をスクリーニングおよび隔離するために別個の措置 (iii)意思決定サポートのためのデジタルテクノロジー(モバイルアプリや災害ダッシュボードなど)の利用等。
ADRCからは2名が防災作業部会等に参加し、2021年の年間運用計画(AOP)の最終化に関する議論に加わりました。2020年のAOPのほとんどは新型コロナウイルス感染により実施できなかったため、2021年は、AOPの活動はオンライン活用も含め継続される予定です。
(2020/12/11 14:40)
(2019/05/24
14:40)


2015年5月25日~27日(バングラデシュ、ダッカ)
 昨年12月にバングラデシュで開催した「IRP復興ワークショップ」では、復興のあらゆる過程において「Build Back Better」を基軸に、それを明確に位置づけることの必要性が求められました。これを受けて、防災・救護省(MoDMR)、バングラデシュ災害復興戦略研究所(ISRSDRR)、国連開発計画(UNDP)との共催で、IRP/ADRCは3日間の「IRP復興ワークショップ」をバングラデシュ、ダッカで開催しました。
昨年12月にバングラデシュで開催した「IRP復興ワークショップ」では、復興のあらゆる過程において「Build Back Better」を基軸に、それを明確に位置づけることの必要性が求められました。これを受けて、防災・救護省(MoDMR)、バングラデシュ災害復興戦略研究所(ISRSDRR)、国連開発計画(UNDP)との共催で、IRP/ADRCは3日間の「IRP復興ワークショップ」をバングラデシュ、ダッカで開催しました。
ワークショップには50名を越える参加者が集まり、バングラデシュ政府の関係省庁や大学、開発機関、NGO、民間セクターから派遣されたハイレベルな専門家によって、「仙台防災枠組(SFDRR)」を踏まえた復興に関する課題について熱心な議論が展開されました。
バングラデシュ政府の防災・救護大臣、Mofazzal Hossain Chowdhury Maya Bir Bikram氏による開会の辞では、「Build Back Better」の考え方を具現化した効果的な災害管理プログラムの確立に取り組んでいくことが述べられ、また、閉会の辞では、情報大臣、Hasanul Haq Inu氏により、「Build Back Better」の取組みは、情報省や広報機関を通して広く推奨することを支援していくことが、参加者に約束されました。
今回のワークショップの成果としては、復興において問題となる事柄を整理するとともに、「バングラデシュにおける災害前の復興計画」に盛り込まれるべき最初の戦略と行動が、参加者によって整理されたことです。こうしたワークショップの成果をベースに、次に実行するべきステップが次のとおり整理されました。
一つは、6月16日にバングラデシュ国会議員を対象に「Build Back Better」セッションを開催することです。法的支援や法制化を必要とする災害リスク低減と復興問題について国会議員への理解を深めてもらうことが目的です。
二つ目は、防災・救護省が、国連開発計画(UNDP)の支援を通じて、「バングラデシュにおける災害前の復興計画」の最初の戦略と行動の策定を進めるために、8月の第1週に「Writeshop」を開催することです。
三つ目は、防災・救護省とBuild Back Better基金との間における調整を通して、既存の政策や計画に係る法的文書において、復興課題の一覧を位置づけてもらうことが重要と考えます。特に計画省が促進する「Delta Plan」において位置づけられることは大変重要です。
四つ目が、防災・救護省の後援のもと、Build Back Better基金が、バングラデシュにおける主要な関係団体との結びつきを深めることが広く支持されることです。そうすることによってInter-Ministerial Disaster Coordinating Council (IMDCC) の開催が可能となり、復興課題が計画に反映されることにつながっていくと考えます。
最後に、Build Back Better基金が、防災・救護省や関係者との協働を通じて「Build Back Better」を促進する新たなプログラムやプロジェクトを提案していきます。例えば、大学や国際的な知識の交流拠点の間で、復興専門家やボランティア、パートナーシップの絶対的数量がある一定ラインを超えることによって、知識共有や交換の促進だけでなく、学校の教育課程においても復興課題が位置づけられることにも結びつくようになります。最初の提案として、そうした絶対的数量を確保することも含まれます。
(2015/06/02 14:40)

2011年8月29日~9月1日 (ハノイ・フエ・ホーチミン、ベトナム)
防災分野におけるICTの活用方策に関する調査の一環として、8月29日から9月1日の4日間にわたり、ベトナムのハノイ、フエ、ホーチミンを訪問し、ベトナム政府の農業・地方開発省や天然資源・環境省などの政府機関及びJICA関係者に対するインタビュー及び関連資料の収集を実施しました。
ベトナムにおける防災分野におけるICTの活用は、気象予測・観測、リスクアセスメントやリスクマッピング、コミュニティや住民への早期警戒報等において着実に進展しています。一部には最先端のICT技術も観測基地を結ぶブロードバンドの導入や携帯電話による自動的な観測などが見られますが、その多くは実験的なものに限られます。
 台風や洪水などの典型的な気候・水関連災害に対する準備は比較的良く進展している一方で、地滑り、土砂災害、地震や火山などへの準備は必ずしも十分とは言えない状況です。例えば、津波の警報システム(警報タワー)が近年ベトナム中部のダナン市で整備され始めたが、まだ十分ではなく、今後の更なる整備が必要です。また、災害対応能力の更なる向上のためには、様々な機関が情報を共有できるシステム、リモーとセンシング、画像情報システム、リアルタイム計測センサーなどの活用が考えられます。
台風や洪水などの典型的な気候・水関連災害に対する準備は比較的良く進展している一方で、地滑り、土砂災害、地震や火山などへの準備は必ずしも十分とは言えない状況です。例えば、津波の警報システム(警報タワー)が近年ベトナム中部のダナン市で整備され始めたが、まだ十分ではなく、今後の更なる整備が必要です。また、災害対応能力の更なる向上のためには、様々な機関が情報を共有できるシステム、リモーとセンシング、画像情報システム、リアルタイム計測センサーなどの活用が考えられます。
なお、本調査の結果は今後の協力案件の形成に活用される予定です。
(2011/09/02 13:10)
2011年6月27日~29日(タイ、バンコク)
 2011年6月27日~29日、バンコクの国連コンフェレンスセンターにて、アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)の主催により、Expert Group Meeting on Regional Knowledge and Cooperation for Comprehensive Multi-Hazard Risk management in Asia and the Pacificが開催され、要請によりアジア防災センターは参加しました。この会合には、各国の代表、国連機関等からの参加があり、①Asia Pacific Gateway on Disaster Risk Reduction and Development、②Data for Disaster Risk Reduction and Assessment、③Regional Cooperative Mechanism on Disaster Monitoring and Early Warning, Particularly Drought、④Asia Pacific Disaster Reportに関し、現在の課題や今後の必要な取り組みについての議論が行われました。アジア防災センターとしては、災害に関するデータ整備の重要性、アジア防災センターが普及している世界災害共通番号(GLIDE)の活用、東日本大震災をはじめとして具体の災害に関する経験の共有の必要性等について説明を行いました。
2011年6月27日~29日、バンコクの国連コンフェレンスセンターにて、アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)の主催により、Expert Group Meeting on Regional Knowledge and Cooperation for Comprehensive Multi-Hazard Risk management in Asia and the Pacificが開催され、要請によりアジア防災センターは参加しました。この会合には、各国の代表、国連機関等からの参加があり、①Asia Pacific Gateway on Disaster Risk Reduction and Development、②Data for Disaster Risk Reduction and Assessment、③Regional Cooperative Mechanism on Disaster Monitoring and Early Warning, Particularly Drought、④Asia Pacific Disaster Reportに関し、現在の課題や今後の必要な取り組みについての議論が行われました。アジア防災センターとしては、災害に関するデータ整備の重要性、アジア防災センターが普及している世界災害共通番号(GLIDE)の活用、東日本大震災をはじめとして具体の災害に関する経験の共有の必要性等について説明を行いました。
また、6月29日~7月1日の日程でUNESCAP防災委員会が開催され、その初日アジア防災センターもオブザーバーとして参加しました。アジア太平洋地域における防災協力に関しアジア防災センターがその実施機関として貢献していることに関し複数の国の代表から言及があり、アジア防災センターとしても引き続き諸活動を通じて各国と協力を推進していくこととしました。
(2011/07/04 13:10)
2011年5月26日~6月4日(ブルネイ、バンダルセリベガワン)
アジア防災センターは、衛星画像の防災利用のための人材育成プログラムを、アジア工科大学(AIT)と協力して、2011年5月26日~6月4日にブルネイ国のバンダルセリベガワンで実施しました。
このプログラムは、講習(1日間)と実習(5日間)が含まれており、ブルネイ国測量局と協力して、プログラムを実施しました。なお、本プロジェクトは、ADRCが2008年から実施しているASEAN10カ国を対象にした4つの防災能力開発事業のうちの一つです。
ブルネイ国では、防災分野での衛星データの利用が進められていますが、衛星データを十分に使いこなせる技術者が不足しており、技術者の育成が課題です。
本プロジェクトでは、防災に携わる技術者や行政担当者を対象に、衛星データ利用のために必要なリモートセンシング技術やGIS、GPSに関する講習及び実習を行いました。
ブルネイ国では、洪水をケーススタディのテーマとし、洪水発生前と洪水発生後の衛星画像の比較をして、洪水氾濫区域の抽出をしました。
本プロジェクトを通して、各国の防災分野での衛星データの利用が更に推進されることが期待されます。
アジア防災センターでは、引き続き、ブルネイ国における防災分野での衛星データの利用を推進してゆきます。本プロジェクトの詳細については、ADRCのウェブサイトを参照下さい(http://www.adrc.asia/top_j.php)。
2011/6/2 13;20
2010年11月5日~11月10日 (西スマトラ州、インドネシア)
本年10月25日の午後9時過ぎ、インドネシア西スマトラ州メンタワイ諸島沖で発生した地震・津波は、メンタワイ諸島の北パガイ島・南パガイ島を中心に500名を超える死者行方不明者が発生するという大災害となりました。
(2010/11/15)
21010年10月6日(ミャンマー、ヤンゴン)
アジア防災センターは、日本アセアン統合基金の資金供与を受けて2008年度からGLIDEを用いた災害データベース構築事業を実施しています。 本事業はアセアン各国より災害情報担当官1名ずつをアジア防災センターに招聘し、GLIDEの理解及びGLIDEを用いた災害データベース構築を目的とした研修を行っております。 2010年度はインドネシア、カンボジア、ミャンマーを対象に同様の研修を実施することとしており、今年度の対象国であるミャンマーの災害情報担当部局とのキックオフミーティングを開催し、本事業への協力と災害情報担当官のアジア防災センターへの派遣について会合を行いました。
(2010/10/07 11:30)
2010年8月11日~20日,タイ,バンコク
2010年8月27日~9月3日,フィリピン,マニラ
2010年9月10日~17日,ミャンマー,ネピドー
アジア防災センターは、衛星画像の防災利用のための人材育成プログラムを、アジア工科大学(AIT)と協力して、2010年8月11日~20日にタイのバンコクで、2010年8月27日から9月3日にフィリピンのマニラで、2010年9月10日から17日にミャンマーのネピドーでの各国で実施しました。
このプログラムは、講習(1日間)と実習(5日間)が含まれており、タイ地理情報技術協会(GISTDA)、フィリピン火山地震研究所(PIVOLCS)、ミャンマー科学技術省(MOST)と協力して、プログラムを実施しました。なお、本プロジェクトは、ADRCが2008年から実施しているASEAN10カ国を対象にした4つの防災能力開発事業のうちの一つです。
タイやフィリピン、ミャンマーでは、防災分野での衛星データの利用が進められていますが、衛星データを十分に使いこなせる技術者が不足しており、技術者の育成が課題です。
本プロジェクトでは、防災に携わる技術者や行政担当者を対象に、衛星データ利用のために必要なリモートセンシング技術やGIS、GPSに関する講習及び実習を行ったところです。本プロジェクトを通して、各国の防災分野での衛星データの利用が更に推進されることが期待されます。
アジア防災センターでは、引き続き、タイ、フィリピン、ミャンマーにおける防災分野での衛星データの利用を推進していくとともに、本プロジェクトをASEANの他の国々に順次展開していく予定です。本プロジェクトの詳細については、ADRCのウェブサイトを参照下さい(http://www.adrc.asia/top_j.php)。
2010/10/06 13:20
2010年6月17日~18日(タイ・バンコク)
ADRCは、2010年6 月17-18日にタイ・バンコクで開催された防災プロジェクトポータルの利用に関するトレーニングに参加しました。本トレーニングは、ISDR アジアパートナーシップ(IAP)のイニシアティブであるregional stocktaking and mapping of DRR interventionsをベースにしたもので、アジア災害予防センター(ADPC)が主催し、UNISDRとアジア開発銀行(ADB) の支援を受けて行われたものです。トレーニングには、IAPやアジア・太平洋地域で活躍する防災関連機関から約30名が参加しました。
月17-18日にタイ・バンコクで開催された防災プロジェクトポータルの利用に関するトレーニングに参加しました。本トレーニングは、ISDR アジアパートナーシップ(IAP)のイニシアティブであるregional stocktaking and mapping of DRR interventionsをベースにしたもので、アジア災害予防センター(ADPC)が主催し、UNISDRとアジア開発銀行(ADB) の支援を受けて行われたものです。トレーニングには、IAPやアジア・太平洋地域で活躍する防災関連機関から約30名が参加しました。
トレーニングでは、参加者は防災プロジェクトポータルの利用について学ぶと共に、ポータルの利用促進や継続性についての意見交換を行いました。本ポータルは、アジア・太平洋地域における防災関係者間での調整や連携を押し進め、活動の重複化を避け、よりよい防災活動計画作成に寄与するものと期待されています。
ADRCは本ポータルに対しインプットを行っていくとともに、アジア・太平洋地域の防災関係者間でのよりよい調整と協力推進のために本ポータルの利用を促進していきたいと思っています。
(2010/06/30 16:50)
平成22年3月8日(バンコク、タイ)
センチネルアジアSTEP2で開発されている新しいWebシステムが4月より運用を開始します。それに伴い、センチネルアジア事務局とADRCおよび、関係機関による会議が、地理情報技術開発協会(GISTDA、バンコク、タイ)で開催されました。会議では、新しいWebシステムに概要、使用方法の説明がおこなわれました。
新しいWebシステムの運用開始に伴い、旧システムは、5月で、運用を中止となります。
新しいWebサイトを以下に示しました。
https://sentinel.tksc.jaxa.jp
(2010/03/30 13:20)
 アジア防災センターは、ASEAN米国技術協力・訓練ファシリティが2009年8月19~20日にシンガポールのシンガポール民間防衛隊(Singapore Civil Defense Force)オフィスにおいて開催したリスク評価・モニタリング及び早期警戒に関するワーキンググループ会合に参加しました。
アジア防災センターは、ASEAN米国技術協力・訓練ファシリティが2009年8月19~20日にシンガポールのシンガポール民間防衛隊(Singapore Civil Defense Force)オフィスにおいて開催したリスク評価・モニタリング及び早期警戒に関するワーキンググループ会合に参加しました。