2013年5月21日~23日(スイス、ジュネーブ)

会場のジュネーブ国際会議場
(UNISDRのHPより)
ADRC及びIRPは、5月21~23日(19及び20日にもプレイベントを実施)の間、スイス・ジュネーブ市国際会議場において開催された「第4回防災グローバル・プラットフォーム(GP)」に参加しました。同会議は、国連国際防災戦略事務局(UNISDR)が主催し、世界の防災関係者が一堂に会する2年に1回の機会です。今年は171の中央/地方政府の代表に加え、国際/地域機関、学会、民間セクター、女性/障がい者/高齢者/子ども等の安全に関する市民団体等から延べ約3,500名が参加しました。
今回のGPの大きなテーマは、こうした防災関係者の力を結集させる機会のほか、防災に関する世界的取組み指針である「兵庫行動枠組」(HFA)の目標年次を2015年に控え、HFAの進捗状況の確認と、それらを踏まえ、次の行動枠組み(HFA2)の在り方に関して議論することです。
GPの開会式は、21日の9:30から大会議場にて開催され、開催国スイス連邦のマウラー大統領、国連のエリアソン事務局次長をはじめ、ナミビア・ニュージーランド等各国の代表が挨拶を行いました。
この後、10以上の会議室に分かれて、参加国等からの公式ステートメント、参加機関の事業内容や研究成果等を紹介する延べ170のイベントが開催されました。
ADRCは、21日の14:45から16:15の間、アジア災害予防センター(ADPC)、アジア防災・災害救援ネットワーク(ADRRN)と共催して、「アジア地域における防災協力~技術革新と協働による災害レジリエンス構築」と題する会合を開催しました。同会議においては、中央政府レベルの防災協力のネットワークのハブであるADRC、アジア工科大学を母体とし特に東南アジア地域において高度な技術協力プロジェクトを行っているADPC及び防災に関するアジアのNPOのネットワークであるADRRNがそれぞれの業務における地域内協力の特長を紹介しました。ADRCからは、中央政府レベルの国際防災協力のgood practiceとして、日本の宇宙航空研究開発機構等各国の宇宙開発機関と連携して実施している「センチネル・アジア」の取組みについて紹介しました。この後討議が行われ、アジアには既に域内協力機関が重層的に存在しており、各機関がその特徴を生かして積極的に協力関係を深めるべき等の意見が出されました。
この会合と前後しますが、当日14:00からJICAと国連開発計画との主催で「防災の経済学-防災投資を通じた持続的開発の推進」が開催されましたが、これは、JICAが昨年度実施した(ADRCは委員として参画)、防災投資が後の経済成長に与える貢献の定量的把握手法の紹介であり、多くの国際機関等から参加がありました。
こういった行事以外にも、期間中には各国・機関間の情報交換等の場が持たれました。22日、ADRCは、昨年12月に新たにメンバー国となったイラン・イスラム共和国の防災組織の高官(ガダミ内務省次官兼防災庁長官)と会談の機会を持ちました。次官からは同国の防災力向上に向けADRCの協力を仰ぎたい由の発言があり、当方からは客員研究員招聘等ADRCの事業の展開により同国の意向に沿いたい旨回答しました。なお、この会談の概要は後日イラン防災庁のHPでも紹介されました。

イラン防災庁ガダミ長官(左)と会談するADRC名執所長
(イラン防災庁HPより)
最終日となる23日には国際防災復興協力機構(IRP)の主催するフォーラムが開催されました。内容の詳細は次の記事をご覧ください。
同日16:30から大会議場において閉会式が開催されました。まず議長(ダニデン・スイス開発協力機構会長)から議長サマリーの案が提示されました。ワルストロムUNISDR特別代表から参加者への謝辞が述べられた後、日本国政府代表の亀岡偉民 内閣府大臣政務官(防災担当)から、日本での開催が決定している次期国連防災世界会議について、2015年3月に仙台市で開催することを表明して3日間の会期を終了しました。

閉会式において次期防災世界会議の仙台開催を発表する亀岡大臣政務官
(画面中央)
(2013/06/13 13:00)
















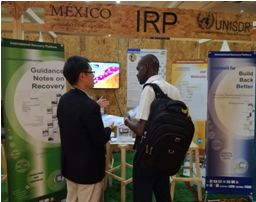














-thumb-300x225-1570.jpg)









-thumb-300x199-1428.jpg)















