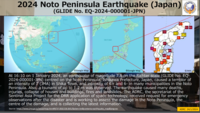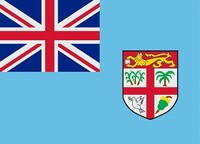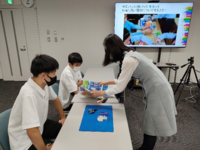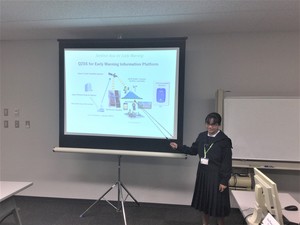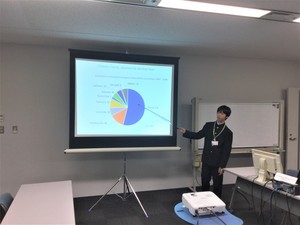ADRC活動報告: テーマ・課題 >> その他
国際復興支援プラットフォーム (IRP)/アジア防災センター(ADRC)は、マニラ気象台の要請を受け、SMプライム(フィリピンの不動産開発大手企業)及びフィリピン災害復興基金と協力し、2016年4月29日にフィリピン、マカティ市のアジア経営大学院で開催された「事前災害復興計画に係るオリエンテーション・ワークショップ」の支援を行いました。
このワークショップには、市民社会(シビル・ソサエティ)や科学界、学術団体、マスメディア、地域社会の代表者など、官民セクターから約90名の参加者が集まり、事前復興計画の本質について学びました。参加者の構成が多様性に富んでいたため、効果的に事前復興計画の演習を実施することが出来、また、復興過程においてお互いの機能を補完的に支援することを促すことも出来ました。
今回のワークショップでは、世界中の災害復興の経験から得られた、戦略、行動、事例研究を含む現時点のツールや経験に基づいて、事前復興計画を策定するための様々なアプローチを探ることが出来ました。特に日本において、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、そして、熊本地震(2016年)の復旧・復興過程で活かされた事前の災害時応援協定や復興支援協定などの経験や教訓は注目を集めました。
また、フィリピンからの著名なスピーカー、とりわけ、マニラ気象台のアントニア・ロイザガ氏、SMプライムのリザ・シレリオ氏、フィリピン災害復興基金のギレルモ・ルーズ氏、フィリピン市民防衛局のアレキサンダー・パマ大将、そして、フィリピン経済開発局のレメディオス・エンデンチア氏から、事前復興計画の重要性について強調する発言が際立ちました。
ワークショップでの発表者は、総じて、事前復興計画が本質的であることを認識しており、さらに、政府関係機関や地域社会のセクターは、災害復興の過程において、同じような組織的、政策的な課題に直面することが、事前復興計画の重要性を高めていると考えていました。例えば、災害に対するガバナンスや財政管理、効果的運用の問題、被災地における再開発基準や輸送の問題、被災者の健康・生活面の問題などは、全てのセクターにおいて共通の課題として考えられます。したがって、事前復興計画をあらかじめ策定しなければ、社会全体で巨大な損失が連動して発生することとなるのです。
事前復興計画を策定することの利点として、まず、第一に、全てのステークホルダーが、分野横断的、学際的、省庁間・部局間が協力して、事前復興計画を策定することによって、復興の速度を速めることが出来ます。また、お互いに協力した計画策定と実行が促され、不明確さや、重複、ボトルネックとなる部分を最小限にすることが出来ます。第二に、全てのステークホルダー間のさらなる強力な関係を構築することが出来て、災害直後のストレス下での不適当な決断を避けることが出来ます。全てのステークホルダーが復興への全面的な参加・協力に備えることによって、自ら積極的に関与し、事前にリスクを知悉したうえで決断をすることが容易になります。最後に事前復興計画の策定は、復興過程を財政的に支援するための仕組み(例:事前復興支援協定や契約によるサービス提供など)をあらかじめ確立することが出来ます。
今回のワークショップでは、フィリピン火山地震研究所から提供されたメトロ・マニラ地域の地震シナリオを使用することによって、主に2つの成果を上げることが出来ました。一つは、「事前復興計画のためのチェックリスト」であり、もう一つは、「事前復興支援協定のひな型」です。今後、参加者は、フィリピン政府災害対策調整会議とともに、今回の議論をさらに前向きに進めていくことに同意し、災害復興過程における事前復興支援協定を実現するための選択肢を調査していくこととなりました。
(2016/04/29 14:40)
2014年6月16日~17日(フィリピン、マニラ)
SMプライムが主催し、IRP/ADRCの協力、UNISDRのグローバル教育研修機関(GETI)の実施による「ビジネス防災ワークショップ」が、6月16日~17日にかけて、マニラのアジア・モール、SMXコンベンション・センターで開催されました。
今回のワークショップは、貿易、金融市場、サプライチェーンが益々相互に結びつきを強め、世界経済や政治が急速に変化しつつあるという認識のもと開催されました。ビジネスは、特に災害時において、従来よりもよりリスクの高い状況に直面します。例えば、2011年の東日本大震災、バンコクの洪水では、企業が大きな被害を受けましたが、世界的企業は災害から企業を守り、災害後もビジネスを継続しなくてはなりません。ワークショップでは、(1)民間セクターのリスク・マネジメントに係る能力や戦略を強化する、(2)投資の妥当性及び持続性を確保し、全てのリスクの可視化を促進する、(3)政府に対し、民間セクターと協力し、防災への投資をより強化するよう働きかけることを目的としました。
民間企業、政府、学術関係者60名以上が参加し、より災害に強いビジネスの実現のために今後どのような戦略、活動が必要なのか等について議論を行いました。IRP/ADRCとして、中小企業の防災についての世界の事例を紹介し、参加者がそれぞれの事業継続計画(BCP)を策定するためのガイダンスや幅広い選択肢を提供しました。
また、ハンス・サイ氏(SMプライム会長)、アレクサンダー・パマ氏(NDRRMCエグゼクティブ・ディレクター)、レナト・ソリダム氏(フィリピン火山・地震学研究所ディレクター)、ホセ・カディズ氏(マリキナ市副市長)、アルフレド・アーキラノJr.(前セブ州サンフランシスコ市長)が地元であるフィリピンの事例について報告されました。
ワークショップでは、防災に関する知識のギャップをなくすこと、また企業オーナーは官民のより緊密な連携によって従来のBCPの枠を超えなければならず、さらには、企業は災害リスクに対応した商品によって市場に新たな価値を創造することを考慮すべきとの提言がありました。
(2014/6/30 14:30)
2012年12月14日(日本、神戸)

12月14日、外務省の招きにより来日中のフダイベルゲノフ・ウズベキスタン共和国非常事態大臣がアジア防災センターに立ち寄られました。
本センターからは、メンバー国の防災関連人材育成やセンチネル・アジアを通じた防災関係の技術協力等の業務概要について紹介しました。大臣からは、非常事態省ではこれまでもJICA研修等の場を通じて日本の防災政策について学ぶ機会を持ってきているが、アジア防災センター客員研究員制度の活用を図り、さらに日本の経験・教訓や知見に学んでいきたいとのコメントがありました。
(2012年12月26日 13:00)
(←フダイベルゲノフ大臣からの記念品の授与)
2012年5月2日(神戸、日本)

2011年2月28日~3月5日,ベトナム,ハノイ
2011年3月14日~3月19日,インドネシア,ジャカルタ
アジア防災センターは、衛星画像の防災利用のための人材育成プログラムを、アジア工科大学(AIT)と協力して、2011年2月28日~3月5日にベトナムのハノイで、2011年3月14日から3月19日にインドネシアのジャカルタで、各国で実施しました。
このプログラムは、講習(1日間)と実習(5日間)が含まれており、ベトナム国自然資源環境省リモートセンシングセンター(MONRE)、インドネシア国立航空宇宙技術研究所(LAPAN)と協力して、プログラムを実施しました。なお、本プロジェクトは、ADRCが2008年から実施しているASEAN10カ国を対象にした4つの防災能力開発事業のうちの一つです。
ベトナムやインドネシアでは、防災分野での衛星データの利用が進められていますが、衛星データを十分に使いこなせる技術者が不足しており、技術者の育成が課題です。
本プロジェクトでは、防災に携わる技術者や行政担当者を対象に、衛星データ利用のために必要なリモートセンシング技術やGIS、GPSに関する講習及び実習を行いました。
ベトナムでは、洪水をケーススタディのテーマとし、洪水発生前と洪水発生後の衛星画像の比較をして、洪水氾濫区域の抽出をしました。
インドネシアでは、津波をケーススタディのテーマとし、津波のシミュレーション結果から、津波の被災区域を抽出しました。
本プロジェクトを通して、各国の防災分野での衛星データの利用が更に推進されることが期待されます。
アジア防災センターでは、引き続き、ベトナム、インドネシアにおける防災分野での衛星データの利用を推進していくとともに、本プロジェクトをASEANの他の国々に順次展開していく予定です。本プロジェクトの詳細については、ADRCのウェブサイトを参照下さい(http://www.adrc.asia/top_j.php)。
2011/03/30 13:20
2011年2月1日~2日(タイ、バンコク)
アジア防災センターは、ASEAN地域の防災能力強化のための衛星データ利用に関する第一回リージョナルワークショップを、2月1、2日に、アジア工科大学の協力のもと、同大学のカンファレンスセンターで開催しました。
このリージョナルワークショップは、アジア防災センターが2008年からASEAN諸国を対象に実施する4つの防災能力開発事業の一つで、防災に携わる技術者や行政関係者を対象実施している、「衛星画像利用の防災利用についての講習や実習」の成果報告や、衛星画像の防災利用についての情報を関係者で共有することを目的として実施しました。
ASEAN諸国、ASEAN事務局、在タイ日本大使館、国際機関から、27名が出席し、衛星画像の利用推進のための活発な討議が行われました。
このリージョナルワークショップの討議のポイントは、以下の通りでした。
1) 宇宙関連機関と防災関係機関との緊密な関係
2) 有効な衛星情報利用と専門知識と技術の開発
3) 災害管理の能力を向上するための宇宙技術以外のICT技術の利用
4) 地域のシステムを通じた国家間での相互学習
アジア防災センターでは、引き続き、ASEAN地域の防災分野での衛星データの利用を推進してゆきます。
なお、このプロジェクトおよび、リージョナルショップの詳細な結果については、ADRCのウェブサイト(http://www.adrc.asia/top_j.php)をご覧ください。
2011/02/21 13:20
2010年10月17日~23日,カンボジア,プノンペン
アジア防災センターは、衛星画像の防災利用のための人材育成プログラムを、アジア工科大学(AIT)と協力して、2010年10月17日~23日にカンボジアのプノンペンで実施しました。
このプログラムは、講習(1日間)と実習(5日間)が含まれており、カンボジア土地管理都市開発建設省地理局と協力して、プログラムを実施しました。なお、本プロジェクトは、ADRCが2008年から実施しているASEAN10カ国を対象にした4つの防災能力開発事業のうちの一つです。
カンボジアでは、防災分野での衛星データの利用が進められていますが、衛星データを十分に使いこなせる技術者が不足しており、技術者の育成が課題です。
本プロジェクトでは、防災に携わる技術者や行政担当者を対象に、衛星データ利用のために必要なリモートセンシング技術やGIS、GPSに関する講習及び実習を行いました。特に、干害をテーマとして、講習と実習をおこないました。
本プロジェクトを通して、各国の防災分野での衛星データの利用が更に推進されることが期待されます。
アジア防災センターでは、引き続き、カンボジアにおける防災分野での衛星データの利用を推進していくとともに、本プロジェクトをASEANの他の国々に順次展開していく予定です。本プロジェクトの詳細については、ADRCのウェブサイトを参照下さい(http://www.adrc.asia/top_j.php)。
2010/10/25 13:20
2010年8月11日~20日,タイ,バンコク
2010年8月27日~9月3日,フィリピン,マニラ
2010年9月10日~17日,ミャンマー,ネピドー
アジア防災センターは、衛星画像の防災利用のための人材育成プログラムを、アジア工科大学(AIT)と協力して、2010年8月11日~20日にタイのバンコクで、2010年8月27日から9月3日にフィリピンのマニラで、2010年9月10日から17日にミャンマーのネピドーでの各国で実施しました。
このプログラムは、講習(1日間)と実習(5日間)が含まれており、タイ地理情報技術協会(GISTDA)、フィリピン火山地震研究所(PIVOLCS)、ミャンマー科学技術省(MOST)と協力して、プログラムを実施しました。なお、本プロジェクトは、ADRCが2008年から実施しているASEAN10カ国を対象にした4つの防災能力開発事業のうちの一つです。
タイやフィリピン、ミャンマーでは、防災分野での衛星データの利用が進められていますが、衛星データを十分に使いこなせる技術者が不足しており、技術者の育成が課題です。
本プロジェクトでは、防災に携わる技術者や行政担当者を対象に、衛星データ利用のために必要なリモートセンシング技術やGIS、GPSに関する講習及び実習を行ったところです。本プロジェクトを通して、各国の防災分野での衛星データの利用が更に推進されることが期待されます。
アジア防災センターでは、引き続き、タイ、フィリピン、ミャンマーにおける防災分野での衛星データの利用を推進していくとともに、本プロジェクトをASEANの他の国々に順次展開していく予定です。本プロジェクトの詳細については、ADRCのウェブサイトを参照下さい(http://www.adrc.asia/top_j.php)。
2010/10/06 13:20
2010年3月20日(インド、グジャラート州、ガンディーナガル)
 IRPは、インドのガンディーナガル市で開催された、グジャラート復興状況報告書に係る州レベルのコンサルテーションに参加しました。コンサルテーションは防災グローバル・フォーラム及びデリー大学の主催により開催され、中央、地方政府、NGO等から20名を超える参加者がありました。
IRPは、インドのガンディーナガル市で開催された、グジャラート復興状況報告書に係る州レベルのコンサルテーションに参加しました。コンサルテーションは防災グローバル・フォーラム及びデリー大学の主催により開催され、中央、地方政府、NGO等から20名を超える参加者がありました。
IRPはプレゼンテーションの中で、一連の復興状況報告書作成の経緯について説明し、知見の構築のためには、復興における優良事例や経験が重要であることを強調しました。特に「グジャラート地震復興状況報告書」は、『よりよい復興』を実現する、中央、地方政府向けの「復興ガイダンスノート」の作成に資するものでもあります。コンサルテーションでは、復興過程での問題、ギャップについての議論、また経験、優良事例、教訓の共有化、及びグジャラート地震からのユニークな復興の経験から導き出されるキーメッセージについての熱心な議論が行われました。報告書はまもなくIRPのホームページに掲載される予定です(www.recoveryplatform.org)。
(2010/04/01 14:30)
2010年3月15日~19日(インド、ニュー・デリー)
各国政府が「より良い復興」を実現するための「復興ガイダンスノート」作成に係る第2回ナショナル・コンサルテーションが、IRPとUNDPインドの主催によりニュー・デリーで開催されました。インフラ、シェルター、気候変動対応、健康、心のケアのそれぞれの分野の専門家50名以上が参加し、インドにおける経験から様々な復興の局面における事例研究、優良事例などが提示されました。ガイダンスノートは、復興活動を強化する「オプション・メニュー」を提供し、その中で政策決定者や実務者は適したオプションを決定します。またガイダンスノートは分野ごとに分かれ、事例研究を中心に証例に基づいたものとなっており、絶えずアップデートを図っています。IRPでは、コンサルテーションに引き続き、神戸でワークショップ、2010年4月にはペアレビューを実施します。
(2010/03/31 14:30)
2009年12月21~23日(ビシュケク、キルギス)
キルギス緊急事態省(Ministry of Emergencies)を訪れ、キルギスにおける自然災害への宇宙技術利用と今後の協力関係の強化について協議しました。
また、中央アジア応用地球科学研究所(Central Asian Institute of Applied Geosciences) において、自然災害に対する宇宙技術利用について協議しました。
(2009/12/24 17:30)
2009年9月27~30日(コロンボ、スリランカ)
スリランカ防災人権省(Ministry of Disaster and Human Rights)および防災施策の実施機関である国家災害管理局(Disaster Management Center (DMC))を訪れ、スリランカにおける自然災害への宇宙技術利用と今後の協力関係の強化について協議しました。
また、Meteorology Department, Survey Department, Coast Conservation Department, National Building Research Organizationにおいて、自然災害に対するそれぞれの役割と宇宙技術利用について協議しました。
(2009/10/06 17:30)
2009年9月9日~11日(ブータン王国)

このプロジェクトは、公共建築物等の耐震化を中心として、地震発生時の被害の軽減および復興のための拠点の確保と的確で迅速な復興活動を可能にする、安全で安心なコミュニティおよび地域を創出することを目的としている。
今回のワークショップでは、ブータン王国政府で作成した地震防災および耐震設計に関するガイドライン等を日本側で再検討し、その再検討の結果をブータン側の技術者に対して説明するとともに、意見交換を行うことであった。
ワークショップには首都ティンプー及びその周辺地域から18名の技術者が参加し、ブータン側が作成したガイドライン等に関して、日本の専門家からそれに対する評価や他の事例との比較結果等について説明を行い、ブータン側の出席者との間で活発な質疑応答や意見交換が行われた。
(2009/9/16/13:20)
2009年9月3~4日 (ジャカルタ、インドネシア)
日本・ASEAN統合基金(JAIF)の事業として既に承認されている、「ASEAN防災人道支援調整センタ(AHAセンター)に関わるフィージビリティ調査」および将来予定されている「通信衛星を活用したASEAN防災情報ネットワークシステム整備」等について、今後のプロジェクトの進め方を、ASEAN事務局、AHAセンター準備事務所等と協議してきました。このうちAHAセンターフィージビリティ調査については、ADRCが実施機関として参加する予定となっています。
JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力 インドネシアにおける地震火山の総合防災策 プロジェクト事務所において、関係者と本プロジェクトの今後の進め方について協議しました。本プロジェクトは、JICA およびJSTの援助で実施されており、インドネシアにおける、地震・津波・火山噴火のハザードに関する研究(グループ1および2)、対策に関する研究(グループ3および4)および研究結果の社会還元に関する研究(グループ5および6)を日本側研究代表者とインドネシア関係省庁と研究機関の代表者で構成されるJoint Coordination Committeeと連携して実施されます。ADRCは「グループ5;防災教育推進と意識向上(代表機関:富士常葉大学大学院環境防災研究所)」および「グループ6;研究成果を生かすための行政との連携(代表機関:アジア防災センター)」に参画しています。本プロジェクトに関するさらに詳しい情報(日本語)は下記のウェブサイトよりご参照いただけます。
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/indonesia/
(2009/09/10 13:10)
 2009年7月15~25日、ネパールにおいて、ERRP(南アジア地域における地震防災対策計画への技術支援事業)のRegional Proposalとして計画している「ネパール カトマンズでの既存住宅の引き倒し実験」についての現地関係先との打合せ、およびネパールERRP/UNDPが国別活動の一環として実施する「Vulnerability Assessment of Buildings/ Retrofitting and Recovery Preparedness for Municipal Engineersに関する4日間のTrainingを実施しました。詳細は下記をご覧ください。
2009年7月15~25日、ネパールにおいて、ERRP(南アジア地域における地震防災対策計画への技術支援事業)のRegional Proposalとして計画している「ネパール カトマンズでの既存住宅の引き倒し実験」についての現地関係先との打合せ、およびネパールERRP/UNDPが国別活動の一環として実施する「Vulnerability Assessment of Buildings/ Retrofitting and Recovery Preparedness for Municipal Engineersに関する4日間のTrainingを実施しました。詳細は下記をご覧ください。Mission Report

2009年3月22日
ADRCでは、アジア工科大学の協力を得て、日本アセアン統合基金による災害対策のための衛星画像利用に関するプロジェクトを実施しています。
このプロジェクトは、シンガポール及びマレーシアを除くアセアン8ヶ国を対象として、防災分野への衛星画像利用を促進するものであり、講習と実習を各国で実施する予定です。
このプロジェクトの実施について、対象各国で、具体的な実施に向けた関係者の連絡・調整のための第1回目の協議会を以下の通りに開催しました。
今後、これらの会議の結果を受けて、講習会・実習ための、資料を作成する予定です。
http://www.geoinfo.ait.ac.th/adrc/index.htm
・2009年3月22日、インドネシア国立航空宇宙研究所
・2009年3月25日、フィリピン国火山地震研究所
・2009年4月23日、ラオス国リモートセンシングセンター
・2009年5月12日、ミャンマー国科学技術省
・2009年6月8日、タイ地理情報・宇宙技術開発協会
・2009年7月10日、ベトナム国立リモートセンシングセンター
・2009年7月27日、カンボジア国地理局
・2010年3月22日、ブルネイ国測量局
(2010/03/30 13:20)
2008 年11 月12日~14日(インドネシア、バリ島)
2008 年11 月12日~14日、インドネシア共和国のバリ島において、アジア防災会議2008(ACDR 2008)が開催されました。インドネシア共和国政府(研究・技術省/国家防災庁)、日本国政府(内閣府)、国連国際防災戦略事務局(UN/ISDR)およびアジア防災センター(ADRC)が主催し、国連人道問題調整事務所(UN/OCHA)、世界気象機関(WMO)が共催し、ADRC メンバー国を中心に、国連機関・国際機関、NGO、民間、学界など24カ国14機関から、防災関係者106名が一堂に会しました。
会議では、HFAについて各国における取組状況を報告し、課題の検証および今後の取組に向けた方向性についての検討を行いました。また、ADRCのマラニシ・プラサド・シャンブ客員研究員(ネパール)およびヴー・タン・リム客員研究員(ベトナム)より、客員研究員プログラムについての紹介とともに現在彼らが日本で取り組んでいる業務についての報告を行いました。会議の詳細につきましては、下記のサイトをご覧ください。
http://www.adrc.asia/acdr2008bali/index_j.html
(2008/11/30 09:50)
2008年7月29-31日(クアラルンプール、マレーシア)
ADRCは、国際協力機構(JICA)と協力し、2008年7月29日から31日にかけて、JICA 草の根技術協力事業「アジアNGO防災研修」の第二年次プログラムをマレーシア・クアラルンプールで実施しました。group_photo-thumb-200x150-54.jpg)
第二年次プログラムは、第一年次の本邦研修の成果を生かし、ADRRN(アジア防災・災害救援ネットワーク)のメンバー間で防災知識や経験の共有を行う目的のもと、第一年次研修員6名およびADRRN からの新たな参加者6 名、ADRRNからのリソース3 名、ADRRN事務局1名、ADRC2名の計18名が参加しました。3日間にわたるワークショップを開催し、第一年次研修員が各国で実施するコミュニティ防災活動、防災ツールであるタウンウォッチング、気候変動やジェンダー問題などをテーマに、活発な意見交換が繰り広げられました。
詳細につきましては、ハイライトVol. 185号(http://www.adrc.asia/highlights/NewsNo185jp)をご覧ください。
(2009/03/16 16:50)