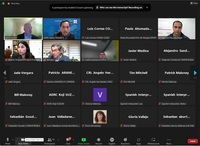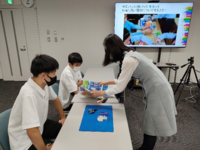2022年11月29~30日(オンライン)
ADRCは、毎年、台風委員会の4つのワーキンググループが開催する統合ワークショップ(IWS)に参加しています。IWSでは、気象ワーキンググループ(WGM)、水文ワーキンググループ(WGH)、防災ワーキンググループ(WGDRR)、研修・研究調整グループ(TRCG)の4つのワーキンググループがそれぞれのその年に行った活動の報告書を発表します。今年は、台風委員会事務局が「早期警報と早期行動のための熱帯サイクロン計画、予測、対応サービス」をテーマに、2022年11月29~30日にオンラインによる第17回IWSを開催しました。
基調講演の一つとして、日本の国土交通省から「洪水シミュレーションとリスク評価への衛星データの利用」について発表がありました。報告されたように、ADRCの協働機関でもあるJAXAといった日本の様々な機関は、衛星データを提供するとともに、気候変動の影響予測データを作成して、洪水のシミュレーションやリスク影響評価を行っています。衛星データの価値は、減災対策に役立つだけでなく、早期の対応を可能にすることです。第17回IWSでは他に、ベトナム、中国、韓国、アジア太平洋台風共同研究センターから基調講演が行われました。
2023年の第18回IWSは、タイ・バンコクのESCAPで開催される予定です。
(2022/12/07 15:00)